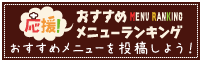www.imdb.comエフゲニー・ルーマン監督は1979年ミンスクの生まれ。
本作と同じ様に1990年に旧ソ連からイスラエルに移住したとのこと。ということは当時11歳だったという訳だ。
旧ソ連在住のユダヤ人のイスラエルへの「帰還」には背景がある↓
https://www.jnpc.or.jp/journal/interviews/33074
監督は11歳だったが本作の主人公たるフレンケル夫妻は60歳代。移住にはさぞかし不安が付き纏ったであろう。母国では洋画の吹き替え、声優をしていた。
イスラエルには既にロシアからの移民ソサエティが出来上がっていた様で、映画のロシア語吹き替えの需要や、ロシア語によるテレホン・セックスの需要まである。
↓俳優のキャリアを見ると彼らもまた映画と同じ移民であることが分かる。
旧ソ連で一体どれくらいの外国映画が観られていたのであろう。恐らく検閲で上映出来ない作品も多かった筈だ。
夫ヴィクトル(ウラジミール・フリードマン)は「クレイマー・クレイマー」('79)の吹き替えをやっていた。またテルアビブの映画館で成人映画を観て「ソ連の規制が懐かしい」と呟く。彼らの中に抜き差し難くある旧ソ連的モラル。疎ましかった筈の国家体制すら懐かしむ異国での老境。
一方、妻ラヤ(マリア・ベルキン)は異国で女に目覚める。旧ソ連的モラルはテレホン・セックスで出会う男によって剥がされ、未だ旧いままの夫が疎ましくなる。
国が配布するイラクからの攻撃に備える為にガスマスクを付けろと強要する夫、頑なに嫌がる妻。国の言うことを素直にきく夫と女の身嗜みを優先する妻の対比。
国家体制に起因する心の内なるモラルというものはどんな人間にもあるという事をこの映画は教えてくれる。我々日本人はこの旧ソ連的なるものを嗤えない。
そんな二人を再び引き寄せるのか1963年にモスクワで会ったフェデリコ・フェリーニの思い出。映画が結ぶ夫婦の絆。映画があって良かった、とも受け取れるルーマン監督の映画愛。
映画館で夫が映写をリクエストした「ボイス・オブ・ムーン」('90)はそのフェリーニの遺作。
そこへイラクからのミサイル攻撃。衝撃でフィルムのコマが焼ける。イスラエルにいる現実が突き付けられる。
旧ソ連にコメディってあったっけ?とふと思い、イスラエルの地で哀愁に満ちたほのぼのとしたコメディを作り上げる事がこの映画の登場人物と同じく、旧態国家体制からの解放であった事に思い至る。
佳作、お勧め。