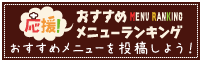撮影中の主役の死去、疫病の蔓延と山田洋次監督の長いキャリアに於いても初めて尽くしの難産、労作だったと思う。
冒頭に松竹100周年記念作品と出る。
さすれば同じような主題の「キネマの天地」('86)はというとこちらは松竹大船撮影所50周年記念作品。
ウィキペディアを読んで思い出したが、そうか、これも主役が降板しているのだ。
まず、若き日の助監督ゴウ(菅田将暉)の撮影所生活の時代設定がよく分からなくて混乱したまま観ていた。年号や時代背景は一切出て来ない。
一方、現代の方はW杯やらコロナ禍やら今の時代感がある。
過去の映画作品が全部架空で、キネマ旬報誌はキネマの友誌に、テアトル銀幕なる映画館もどこにあるか分からない架空のものになっているが、ビールは現実に存在するスーパードライ。飲んでる人は全員何が何でもスーパードライ。
ラスト、コロナ禍の映画館に老いたゴウ(沢田研二)が孫とやって来て、小津の「東京物語」('53)と思しき映画を観る。本編エンドロールにしっかり「東京物語」のフッテージを使っている事が示されている。これを仮に2020年としよう。
当時、この映画に助監督応援でついたと語るゴウ。仮にこの時を30歳前後としよう。すると2020年のゴウは91歳前後である。山田監督の実年齢が89歳。
ゴウの師匠格・出水宏(リリーフランキー)は明らかに清水宏監督だろう。
遺作「母のおもかげ」は1959年(未見)。という事でこれは1950年代の日本映画黄金期の話であるということが判る。
若き日のゴウ助監督がしたためていた脚本は明らかにウディ・アレンの「カイロの紫のバラ」('85)の剽窃である。ゴウは年老いてからそれを孫と一緒にリライトし、賞を取った後で「キートンのアイデアを頂いた」と言うが、どう見てもバスター・キートンの「探偵学入門」('24)からヒントを得たアレンから、だろう。
百歩譲ってキートンだとして同僚のテラシン(野田洋次郎)は何故それに気が付かない?そして城戸賞ならぬ木戸賞の審査員はキートンやアレンの剽窃はOKという事なのか。
年老いたゴウの孫が自室に貼っている夥しい数の標語は一体、と思っていたがどうやら発達障害だということが観ている間に分かる。その特性を「活かして」かなり強引なストーリー展開となる。
沢田研二はとても緊張して演じているのが伝わる。「東村山音頭」を歌う楽屋オチは素直に受け止めたい。
キネマ旬報8月下旬号のレビューは福間健二氏以外は大本営発表だ。そういう位置にある映画なのだが、大雨の西宮北口、100席弱の映画館は満席だった。ちゃんと勝っている。