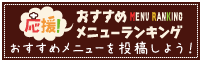弟とアンドロイドと僕 | キノシネマ kino cinéma 配給作品
阪本監督の「団地」(2016)のプロモーションの時だったと記憶しているが、阪本監督にインタビューしている女性が映画の中の表現を誤読していて監督に窘められていた。
ことほど左様に映画本来の「画で語る」という原則が疎まれ、言葉(台詞)で説明することが当然のようになってしまっている幼児向け日本映画、案の定ウェブ上に跋扈する本作に対するシロートレビューもそんなエーガで育ってしまった印象のものが目立つ。
冒頭から「羅生門」並みの豪雨、映画の最後まで止まない。路上で行き倒れている人を運ぶ救急隊からどこかの大学の数学の講義をする主人公・薫(豊川悦司)のモンティパイソンのシリーウォークのような動きに繋がる。
彼を大学の前で待ち構えている弟と思しき人物(安藤政信)。弟の語る父の危篤、開業医だったらしい。
薫が帰る家はホラー映画に似つかわしい廃病院。父の病院なのか?フラッシュバックする暖炉の炎。炎の中で燃えているのは当初は人形かと思えば、やがて薫の母なのではないかと思い至る。
それら提示される断片から「ある家族」の姿が浮かび上がり、その家族によって薫の人格が分裂していることが推測される。そういう推測に至るまでのヒントの収集が本編の面白いところである一方、それに気が付かない客は置いていかれる。
薫は解離性人格障害だと思う。
www.e-healthnet.mhlw.go.jp 昨年の映画「ファーザー」(2020)で認知症の人間の見えている世界をアンソニー・ホプキンスが演じていたが、ここでは解離性人格障害からみた世界、もう一人のアンドロイド薫を製作することで喪われた自分の「あるべきかたち」を完成させて「一人」になろうとしている。
この薫が現在の阪本監督自身の精神状態であるかどうかは計り知れないものの、少なくとも自覚的ではあると思う。
公開規模が小さいようだがかつて東京・大阪だけで封切られていたATG作品を彷彿とさせる。あの頃の大島渚や吉田喜重に比べれば、阪本順治は丁寧にヒントを出していると思う。キャメラ・照明・美術一級品。なにより、この企画に投資したスポンサーに敬服する。