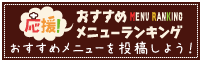監督のラジ・リはマリ出身。マリは旧フランス領だが、国民の90%がイスラム教徒だとのこと。その事はこの映画に深く影響を与えている。
冒頭、エレベーターの無い団地の一室から柩が運び出される。担いでいるのはアフリカ系の移民たちである。
井筒和幸監督「パッチギ!」(2004)で、京都の朝鮮人集落のバラック家屋から柩を出すのにドアを壊すシーンを思い出す。差別される側の死して尚、という意味では同じモチーフだ。
一転、その団地を建て替えるために爆破するというセレモニーが始まる。爆破の衝撃で演壇に立っていた市長が発作を起こして急死。この一連のオープニングは鮮やか。
急遽、代議士投票で小児科医が新市長となる。前任者の任期を引き継ぐ制度なのか、次の市長選挙までの暫定市長なのだが、俄然張り切って移民排除政策の強化に乗り出す。
副市長は移民出身だが権力に寄り添う世渡り上手。一方、市役所に勤めるアビー・ケイタ(アンタ・ディアウ)はアフリカの現地語のほかフランス語も英語も話す。聡明で日々移民の苦情や困り事に対応している。
そこへ英語を話すシリア系の移民が就職して来る。どうやら新市長夫人の「紹介」らしい。彼女とその父親が「優遇」されるのは彼らがキリスト教徒だからである。
フランスは自由と平等の国である一方、その権利を獲得する為には同化を求める。それが義務と言っても過言ではない。信教の自由はあるが、キリスト教もまたその重要なファクターである。
ここでのシリア移民への「依怙贔屓」はやや強調が過ぎる描写だが、恐らくムスリムであろうラジ・リ監督の力点でもある。
アフリカ系移民への圧力が強まり、団地からの総立ち退きへと事態は悪化する。アビーは猛反発し、市長選挙への立候補を宣言する。民主主義の手段と権利で闘おうとするアビー。
突然の総立ち退き命令はクリスマス当日。この設定は流石に違和感を感じざるを得ない。反キリスト教のメタファーとしてのクリスマスの蛮行に見えた。
そして、この大規模な立ち退きの描写は見事な迫力があるものの、その後のアビーの彼氏ブラズ(アリストート・ルインドゥラ)が怒りを爆発させて起こすある行動(ここでは伏せておく)への脚本上の仕掛けである事が透けて見える。
単純な話し、クリスマスにそんな大規模で過酷な「労働」をフランス人がする筈がないと思う。クリスマスには戦争すら休むお国柄である。ここにも宗教上の力点を感じてしまう。
和解も解決もない。ラストの暴力よりも選挙の結果が知りたかった。力のこもった描写には感服するが、惜しい。