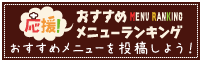これから#女優時代 みる#大森一樹 pic.twitter.com/YSMWsPrxtS
— 白羽弥仁 (@makemydmitts11) 2022年11月20日
図らずも大森一樹監督追悼上映となってしまった宝塚映画祭のプログラムの一本。
1988年読賣テレビ制作のテレフューチャー。
ルックから推しはかると16ミリフィルム撮影、ポジからのデジタルシネマ化、所々シミが見受けられたのでニュープリントではなく初回TVオンエア時のままの上映と思う。シミは映画内映画の効果かと思って観ていたらそうではないパートでもあったので経年劣化故だろう。また屋内ロケのシーンでの同時録音にフィルム撮影のローリングの音が丸っぽ入っていてびっくり。映画ならNGだが当時のTVオンエアの音響レベルなら気がつかないという判断だったのか。
TVオンエア時にVHSで録画、何度か繰り返して観ているがあらためてスクリーンで観ると何と豊かな画面づくりなのかと感心しきり。今のテレビドラマのゆうに三倍くらいの予算が掛けられている筈。という事は現代の映画並み、こうして観ると映画としても充分の味わい深さである。
冒頭の戦前の阪神深江駅はオープンセットだろう、宝塚大劇場の旧館、御影公会堂、旧大映京都撮影所。つくづく映画は20世紀までのメディアだったとの思いを抱く。黒沢清「スパイの妻」(2020)の戦前の神戸を表現するロケーションの窮屈さに比べて、1980年代の何と伸びやかな情景の広がりよ。
斉藤由貴を筆頭に相楽晴子、峰岸徹、室井滋、森本レオ、上田耕一の大森ファミリー、東映映画史から川谷拓三、日活映画史から山本陽子、そして東宝映画史から小林桂樹。
今回観て黒澤明「用心棒」('61)の看板が掲げられた日劇が映り込んだ記録映像がはさまれているのに初めて気がついた。
乙羽信子の一代記と並行して戦後日本映画史を駆け足で巡る楽しさ、豊かさ。
阪急グループに愛され、'80年代という時代と並走した大森一樹版「アメリカの夜」('73)の幸福が画面から横溢している。
終映と同時に拍手が起きたよ大森さん。
![映画に愛をこめて アメリカの夜 特別版 [ ジャクリーン・ビセット ] 映画に愛をこめて アメリカの夜 特別版 [ ジャクリーン・ビセット ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5548/4548967235548.jpg?_ex=128x128)